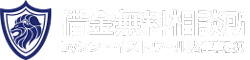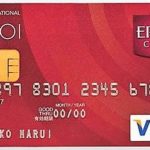アパート、賃貸マンション、戸建ての貸家など、賃貸物件に住んでいる人にとって、月々の家賃を支払うことは当然の義務です。
しかし、病気やリストラ、失業などにより、払いたくても払えなくなってしまう人が大勢いるのも事実。
では、家賃を延滞してしまったら、どうなるのでしょうか?
すぐに大家さんが勝手に荷物を運び出してしまうことはない
家賃を決められた日までに納めなければ、大家さんや管理会社から督促を受けます。電話が来たり、家まで訪ねてきたり。
中には「払えないならすぐに出ていってください!」などと言う人もいるでしょう。
家賃が払えないなら、借りている部屋は明け渡さなければなりませんね。しかしそれでもあなたが出ていかなかったら?
大家さんがやってきて、勝手にあなたの荷物を運び出してしまうでしょうか?あなたが外出している間に、勝手に鍵を変えられてしまう?
いいえ。大家さんは決してそんなことはしません。なぜか?
それは、違法行為だからです。
これらの行為は「自力救済」と呼ばれ、法律で禁止されています。
ひと昔前は、怒りに駈られてそれらの行為をする大家さんや、管理業者がいたみたいですが、それを実行して損害賠償請求された人が大勢います。
もしあなたが、そのような目に遭ったら、すぐに身近な法律の専門家に相談してください。ケースによっては住居侵入罪も成立し、刑事告発する場合もあるので弁護士に相談することをお勧めします。
話はそれますが、家賃の滞納は誰に相談したらいいのでしょうか?
最初に思い浮かぶのは大家さんや管理会社さんでしょう。でも、相談しづらい、怒られそう、などのイメージがありませんか?少し待ってもらえるケースもありますが、根本の解決は難しそうですね。
そこでおすすめしたいのは家賃を滞納してしまったら法律の専門家に相談することです。場当たり的な対応ではなく、長い目線で貴方がどうしたら健全な生活を歩めるかトータルでアドバイスしてくれるでしょう。
法律の専門家は、弁護士の他に、司法書士、行政書士などがあります。もしあなたが今、家賃の滞納が解消できずに困っているなら、早い段階で法律の専門家に相談することをお勧めします。ただ、家賃滞納の根本原因は多重債務であることが多いので、破産申し立ても含め制限なく債務整理ができる弁護士に相談するのがベストです。(司法書士では140万円を超える借金の整理や破産申立ができません)
その名は「建物明け渡し訴訟」

さて、自力救済ができない大家さんたちは、どういう手を使ってくるでしょうか?
最もオーソドックスなのは、裁判所に「建物明渡訴訟」を提訴してくることです。言い方を変えれば、基本的にこの裁判を経ずに、強制的かつ合法的に入居者を退去させる方法はありません。
家賃滞納「3ヶ月以上」が鍵
家賃滞納が発生しても、すぐに家賃滞納者を強制退去させることは出来ません。法的に一定の決まりがあるわけではありませんが、目安としては最低3ヶ月以上家賃滞納が継続してからでないと、強制退去は困難と言われています。
信頼関係破壊の法理とは
建物の明け渡しを求めるには現在締結している賃貸借契約を解除する必要があります。そして、解除するには契約違反(債務不履行)があったことが必要です。
では、1か月分でも家賃滞納(債務不履行)があれば解除ができるかというとそうではありません。
賃貸借契約のような継続的な契約は、当事者間の関係も長期に続くので、一回的な契約よりも、より高度な当事者間の信頼関係を基礎としているので、当事者間の信頼関係を破壊したといえる程度の債務不履行がなければ、その契約を解除することはできない、とされています。これが最高裁判所で認められた「信頼関係破壊の法理」です。
具体的には、賃料滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合には、よほどの事情がない限り、1か月分だけ賃料の滞納があったというだけで解除することはできません。
通常は、少なくとも3か月分以上の賃料滞納がなければ、賃料滞納を理由として契約を解除することはできないと考えられています。
強制退去が実行されるのは裁判が提訴されてから5ヶ月後
明渡訴訟を提起してもすぐに判決、つまり退去命令がでるわけではありません。強制退去に至るまでの手順や段階については後ほど解説していきますが、訴訟の提起からはおよそ5ヶ月で判決が出て、この債務名義(判決文)をもとに強制退去(強制執行)を執行裁判所に申立することができます。
すぐに出て行ってほしくても、実際は手続きにはこれだけの期間がかかるということです。
強制退去が認められない場合も
家賃滞納をしている借家人が失業中、入院中またはそれ以外のやむをえない理由があった場合、建物明渡しは大家側の「権利の濫用」とみなされることもあり強制退去が認められないケースもあります。
このように裁判所を通じて強制退去を実現するにしても時間がかかるのです。
さらにここで問題になるのが、あなたの大家さんの「本気度」それから、あなたの借りている物件の間取りです。
本気度はともかく、なぜ間取りが?
これは、賃貸物件にはそれぞれ「訴訟物価格」というものがあり、その価格により、どのレベルの裁判所で扱われるかが決まるからです。
訴訟物価値は、普通「固定資産税評価額」という市町村が決める建物の価値を基準に計算されますが、一般的には、建物が新しく、鉄骨造りなど頑丈で、間取りが広い部屋の方が高くなります。
そして、この価格が140万円以下ならば簡易裁判所で裁判ができ、140万円を超えると地方裁判所になります。
司法書士が代理できるのは140万円まで
訴える側からみると、このどちらの裁判所で扱われるかが、大きな問題になるのです。
裁判を起こすと聞いて、最初に思い浮かべるのは「弁護士に頼む」ということでしょう。
そして、裁判で勝てば、入居者に対し「住んでいる部屋を明け渡せ」「溜まってる家賃を支払え」との命令は出してもらえるでしょうが、「弁護士費用を支払え」との命令はなかなか出してもらえません。(どうしても取りたければ、また別の裁判を起こさなければなりません)
つまり大家さんからすれば、家賃を払ってもらえず、裁判をしても回収できるかも分からないのに、さらに弁護士費用まで負担しなければならない。かなりの費用負担をする覚悟がなければ、裁判にまでは踏み切れないのです。
でも、今のはすべて、地方裁判所でのお話。
ワンルームアパートなどで訴訟物価格が安く、簡易裁判所に提訴できる場合だと、弁護士に依頼しなくても、例えば建物の持ち主が高齢者の場合なら、息子さんなどの家族が代わりに訴状を出したり、裁判に出たりすることができます。
もし貸し主が会社だったら、その会社の社員が代わりに裁判に出られます。
また現在は法改正により、140万円以内の簡易裁判所の裁判に限り、弁護士より費用が安価な司法書士に委任することができるようになっています。
つまり、大家さん側からすれば、地方裁判所に訴えなければならない場合は負担が大きく、簡易裁判所なら、そうでもないのです。
逆に家賃が払えなくなった入居者から見れば、訴訟物価格が高い物件に住んでいるならそう簡単に訴訟にはならないかも知れませんが、安い物件だと、わずかな延滞ですぐ訴訟を起こされてしまうリスクが高い、とういことになります。
勿論大家さんの中にはこうした違いがあることを知らず、裁判なら何でも弁護士に頼まなければならないと思い、裁判を敬遠している人も結構いるのです。
まずは訴状が届いてから

さて、延滞の程度や訴訟物価格によりますが、いずれにしても、裁判が始まってしまったとします。
どうしたらいいのでしょうか?
あなたに早急に延滞を解消する力がないのなら、裁判中にも延滞は続き、最終的には判決で明け渡しの命令を受けることになります。
しかしそうは言っても、裁判が始まって1か月やそこらで、この命令が出るものでもありません。
ここでお断りしておきますが、この記事は、家賃を払いたくない人に、タダで貸家に長く住む方法をお教えするものではありません。
住んでいる貸家の家賃が払えなくなってしまったなら、親や兄弟などを頼り、同居させてもらうとか、失業してしまっているなら就職活動をがんばって、収入を得られるようにするとか、公的な補助を受けるなど生活を立て直す努力をしてください。
ただそのためには時間が必要。そしてその時間は長いほど有利です。
どういう流れになれば、裁判が迅速に行われ、建物の明け渡しの判決が言い渡されてしまうのか?
ここではそれをお教えしておきましょう。 大家さんが自分で、または弁護士や司法書士に委任して、裁判を起こすと、まずは「訴状」と呼ばれる書類があなたの元へ送られてきます。
訴状には、その裁判の相手(あなたですね。被告と呼ばれます)の住所と名前、裁判でどんな判決を言い渡してほしいか、その理由などが書かれ、契約書のコピーなどの証拠が添えられています。
この訴状は、郵便局の配達員が配達に来ます。
当たり前ですが、裁判は裁判所で、日時を決めて行われます。訴状と一緒に第1回期日に出頭する旨が書かれた呼び出し状も送られてきます。しかし、その日時までに訴状が被告に届かなかったら?
その日時は延期になります。
裁判所の規模にもよりますが、大きな所だと多くの裁判を抱えているため、一度期日が延びると次は1ヶ月後、などということもあります。
最終的に、裁判所が、「被告はわざと訴状を受け取らないようにしている」と認めれば、付郵便(書留郵便に付する郵便)というやり方で、あなたに訴状が届いたことにしてしまうため、いつまでもということはありませんが、それでも最初の配達で受け取った場合に比べれば、1か月以上も遅くなることになります。
裁判所へ行こう!

訴状が届き、裁判が開かれると、そのあとの流れは早いです。
その時点でそれなりの家賃延滞(通常3ヶ月分以上と言われています)があると認められ、被告からなんの反論もなく、裁判にも来ていない、となれば、早い所だと最初の裁判の日で裁判を終わりにし、判決を言い渡す場合もあります。
よく面倒で対応しないという方がいらっしゃいますが、裁判が始まったら、無視はダメです。
裁判所から送られてきた訴状などの書類を無視し、何の書面も出さず、連絡もしないでいると、裁判所から「原告の言っていることはすべてその通りだと認めます」と言っているものとみなされてしまうからです。
反論と言っても何も「家賃はキチンと払っています」などと嘘の主張をする必要はありません。「払ってないことは認めます。今生活が苦しいのでもう少し待ってください」「弁護士に相談しているので次回期日を長めに設定してください」「分割払いの和解を希望します」といった内容でも良いのです。
また、指定された日が、仕事などで都合が悪ければ「その日は仕事で行けません。◯月×日にしてください。」とだけ書いて裁判所に提出してもよいでしょう。
裁判所は、公平の観点から訴訟代理人(弁護士)をつけていない裁判の当事者(とくに被告)に対してはある程度擁護する姿勢で裁判を進めますので、あなたの言い分は遠慮なく裁判所に伝えましょう。
和解と控訴

「訴訟上の和解」について
裁判の終わり方として、判決言い渡しの他に、「和解」というものがあります。
和解といえば普通は仲直りという意味ですが、具体的に建物明け渡し訴訟の場面では、あなたが「これからはちゃんと家賃を払います。たまった分は分割払いで◯◯までに清算します」と約束をして、代わりに、約束を守っている限りは今まで通り住んでいてよい と認めてもらう、といった内容になります。
また、あなたがすでに転居先が決まっている、または目処がついていて、引っ越しまでに時間の猶予がほしい、という状況だったら
「借りている部屋は◯◯までに退去します。たまった家賃は分割払いで……」といった内容にすることもできます。もっとも、いずれも原告(大家さん側)が拒否したら成立しません。
あなたが、裁判が開かれる日に裁判所へ行き、和解したいと言えば、原告が「話し合いの余地はない」と言わない限り、裁判官が、和解が成立するよう尽力してくれます。簡易裁判所の場合には、法廷とは別室に移動してそこで、「司法委員」という人を交えて話し合うことになります。
そこであなたが出した条件(たまった家賃をいつまでに清算できるか、など)を原告が認めれば、和解成立です。
訴訟上の和解が成立すれば、和解調書という書面が作成されます。
ただしこの和解調書には、普通「あなたがその約束を守れなかったらどうするか」ということについても明記されます。
そして、訴訟上の和解が、ただの約束ごとと大きく違うのは、もしあなたがそこに書かれたことを守らなかったら、裁判の判決で、命令を受けたのと同じことになってしまう、という点です。
例えば和解文に「◯◯の支払いを怠った時は、ただちに住んでいる部屋を明け渡す。」という意味のことが書かれたとします。
それは、あなたが支払いを怠ったとたん、「被告は住んでいる部屋を明け渡せ」という判決を受けたのと同じ意味になります。
するとどうなるか?
原告側は、強制執行ができるようになるのです。
訴訟上の和解の大きなデメリットのひとつに、「控訴ができなくなる」
ということがあります。
控訴とは、裁判の判決などに納得が行かない場合などに、上のレベルの裁判所で裁判をやり直してもらうことです。
最初の裁判が簡易裁判所なら、2回目は地方裁判所。最初が地方裁判所なら、2回目は高等裁判所になります。
家賃の滞納をし始めてしまったら早めに相談を
今回は家賃を滞納してしまったらどの様になるのかを解説しました。住居がなくなってしまうのはとても大変なことです。借金などで首が回らなくなってしまい、家賃が払えないのであればまずは弁護士に急いで相談してください。
最適な解決策を提案してくれるはずです。今は無料で相談にのってくれる法律事務所も増えてきましたので、まずは気軽に相談してみましょう。
シン・イストワール法律事務所では借金相談は無料で承っております。是非お気軽にお問い合わせください。