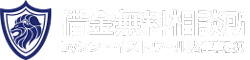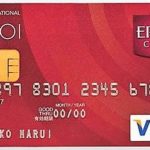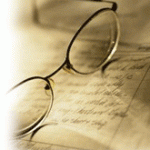1 まず、どのような場合に企業の再生・整理を検討しなければならないのか
企業はお金を儲けることを第一の目標としています。当たり前のことですが、まずは、決算の結果が赤字なのか黒字なのかという点に着目します。
もちろん、企業の経営は山あり谷ありです。当該年度が赤字の場合でもその原因が、例えば、設備投資をしたことや、売掛先の倒産で回収が焦げ付いたことなどの一過性のものであれば、それほど心配することはありません。
しかし、赤字の原因が構造的なものであれば,清算や再生を検討する必要があるでしょう。例えば、そもそも売上に占める経費(原価、固定費、人件費、広告費など)が過大で利益を圧迫しているような場合です。
また、赤字の原因が構造的なものではないものの、3期にわたって赤字が続くようならばかなりまずいと考えましょう。これはそもそも稼ぐ力がない証拠ですから、やはり清算や再生を検討する必要があるでしょう。
2 再建型と清算型がある
構造的な赤字の場合や3期以上赤字決算となった場合、経営者としては、その会社を再生させるのか、それとも清算するのかの判断を迫られます。
では、企業を再生させるべきか否かはどうやって見極めればよいのでしょうか。
ポイントは2つあります。
1つ目:営業利益が黒字であれば再生させるべきでしょう。
営業利益が黒字であれば、企業としての体力(稼ぐ力)があるので長い目でみれば再生は可能とえいます。一時的に資金繰りに窮しても、営業そのものが順調なら、債権者も再生に協力的になります。
2つ目:その企業を存続させる社会的必要性が高い場合にも再生させるべきでしょう。
その企業がその地域にとって必要性の高いもの、逆に言うと、その企業が倒産すると甚大な結果が予想されるような場合です。そのような場合には、債権者も協力的になるでしょうし、スポンサー企業も現れやすいからです。
逆に、上記の2点に該当しない状況なら、コスト構造を抜本的に見直すか、それが無理なら潔く(いさぎよく)清算すべきでしょう。
3 企業再生を可能にするための具体的な方法とは
法的な手続きとしては、民事再生や会社更生手続きなどがあります。
これらの手続きは法律に基づいて、裁判所の監督下で手続きが進められるため不正が入り込みにくく、すべての債権者が公平に扱われるというメリットがあります。
反面、手続きが複雑であり時間や費用がかかる、「倒産企業」のレッテルを貼られてしまい、取引関係に影響が出てしまうというデメリットがあります。
私的整理とは、裁判所を介さず、債権者と債務者との自主的協議により整理・再生を行う方法です。具体的な制度としては、中小企業再生支援協議会・事業再生ADRがあります。また、多少の資金繰り悪化といった状況なら、専門家のアドバイスのもと銀行債務のリスケ(リスケジュール)や新規融資などを試みるべきです。
私的整理は裁判所を介さないため、手続きが簡素であり、柔軟で迅速な対応が可能となります。また、「倒産企業」のレッテルを貼られることがないので既存の取引関係を維持できるというメリットもあります。
反面、債権者を法的に拘束できないので、全債権者が再建計画に同意しないと再生自体が難航することになります。また、民事再生のように「債務弁済禁止」や「強制執行の禁止」等の保全処分を裁判所に申し立てることができないので、一部の債権者によって訴訟を打たれ、再生計画の障害になってしまうという懸念もあります。
4 民事再生について解説
<会社の民事再生とは>
民事再生とは民事再生法に基づいて、経済的に行き詰まった企業を再建させる裁判手続きです。
裁判所の関与のもと,現経営者の続投を前提に,会社財産を一定の範囲で維持しつつ,会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に策定した再生計画を遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図ります。
但し、民事再生手続きによって法的に圧縮できる債務は、無担保債権者に対するものだけに限定されます。よって、抵当権などの担保権を有する債権者に対する債務は従来通りなので、手続き開始後も担保権者は担保の実行をすることが可能です。また、租税債権も対象外です。
会社更生 手続きと比べると、拘束する債務の範囲が限定されている反面、低廉かつ迅速な手続きであるため中小企業向きの手続きといえます。
<民事再生のメリット>
民事再生をした場合には、次のようなメリットがあります。
①事業を継続できる
破産と異なり、民事再生は事業を継続することが前提です。よって、従業員の雇用を守ることができます。また、経営者が法人の債務を保証しているような場合、破産なら経営者個人も破産しなければなりませんが、民事再生ならその必要はありません。
②借金の一部免除や弁済猶予(原則最大10年)が受けられる
債務の一部免除や弁済の猶予を受けつつ、収益力ないしは競争力のある事業を再構築することができます。
③経営権を維持できる
会社更生と異なり、現経営者は原則として退陣する必要はないので、今まで通り会社経営権を維持することができます。現経営者に特殊な技能やスキルがある場合にはこれを活用が可能です。
<再生計画のパターン>
民事再生の再生計画には以下のようなパターンがあります。
①自力再建型
企業の営業利益から再生債権を弁済するパターン
②スポンサー型
支援企業(スポンサー)から資金の援助のもと再生計画を遂行するパターン
③清算型
裁判所の許可を得て、営業の全部または一部を受け皿会社に移管(営業譲渡)したうえで、旧会社は清算するパターン。営業譲渡代金を弁済原資として再生計画を遂行する。
<民事再生を検討するうえでの注意点>
民事再生手続きは、経営者がそのまま経営を続けることを前提に無担保債権を大幅カットすることができるので、経営に行き詰った経営者にとっては「希望の光」のように思えるかもしれません。ただし、以下のような点に注意すべきです。
①営業利益の黒字が絶対条件
民事再生を利用するには、原則として会社の営業利益が黒字であることが絶対条件です。商売の構造上、過大な経費が利益を圧迫している結果、赤字となっているような場合には民事再生を申立ててもおそらく失敗します。このような場合、再生計画をどの債権者も信用しないからです。単に「破産するより民事再生の方が、より多くの配当を得られる」という説明だけでは、債権者は納得しないことを承知すべきです。
②社会的なニーズが強いこと
その企業が存続することへの社会的ニーズが高い場合には、債権者も協力的であり、支援企業(スポンサー)も見つかりやすいので、民事再生を選択する意味があります。また、その企業が特殊な技術や際立つブランドをもっているような場合にも同じことが言えます。
③担保付き債権や租税債権はカットできないこと
民事再生でカットされる債権はあくまで無担保の債権です。担保付き債権(抵当権を付けて借りた銀行借入れ)や租税債権(未払いの税金等)は減額できません。よって、民事再生とは別途、担保権者と交渉して担保実効をしない旨の協定を結んだり、課税庁との分納交渉が必要となります。
④取引先を失うリスク
民事再生を行うと、大切な取引先との債権は大幅にカットされるため、取引先との関係が悪化し、今後の事業に負の影響がでることも想定すべきです。そのため、大口の取引先に依存しているような業態ではリスクが高くなります。他方、販売先が一般消費者を相手に商売をしている場合や特殊な技術、際立つブランドをもっていて特定の債権者に依存する必要がない場合には、民事再生により取引先を失うリスクは最小化されます。
⑤経営者の交代が求められることも想定すべき
経営破綻に至った事情にもよりますが、その原因のほとんどが経営者にあるような場合には、債権者から経営者の交代が求められる場合も少なくありません。ただ、営業利益が黒字であれば、基本的には現経営者の続投も納得してもらえるでしょう。
⑥当面の資金繰り対策が必要
民事再生による再生計画が認可されてその履行を開始するまでの間(少なくとも6か月)、以下のような資金が必要となります。スポンサーでもいない限り、新たな借入れは困難なため、事前にその用意(キャッシュ)が必要です。このような資金を用意することができないのであれば、そもそも民事再生を利用するのは難しいと考えてください。
・民事再生の手続費用及び弁護士費用
最低でも1000万円程度は必要です。
・再生計画の履行が開始されるまでの間の仕入れや固定費・人件費などの運転資金
・公租公課の支払
当面、未払いの公租公課の支払が必要なので、課税庁と分納協議に着手します。また、再生計画が認可されると借金が大幅にカットされることになるので、その債務免除益に対して法人税が課税されます。
<民事再生の流れ>
再生手続開始の申立ての流れです。
・株式会社のみでなく、特殊法人、個人等、幅広く利用できる。
・民事再生の申立てをしたことを金融機関に通知することによって、通知後にその金融機関の口座に入金された債務者の預金については金融機関による相殺が禁止される
・担保権は再生手続きが行われていても実行できる。
保全処分(申立と同時)
・強制執行の中止命令
⇒再生計画認可後は担保権が実行可能となる。
・会社財産処分禁止の仮処分
・公租公課は再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。
再生手続開始の決定(申立から1週間位)
・原則として事業は継続。債務者を監督する監督委員が選任されるが、経営者は続投する(この点が、会社更生法との大きな違い)。
ただし、裁判所の判断により,例外的に管財人が選任された場合には、経営者は、自ら事業を継続することはできなくなる(経営者に問題があって倒産に至った場合)。
・原則、株主の権利は維持される。ただし、「減資条項」が再生計画に定められることがある。
再生債権の届出(申立後1か月位が届出期限)
再生債権(権利変更)の対象となるのは、無担保かつ優先権のない財産上の権利に限られる。
負債総額の確定
再生計画案の提出(申立後3か月位が提出期限)
債務者が再生手続の機関となるため、債権者に対して、公平誠実義務を負う(民事再生法第38条第2項)。
再生計画案の決議(申立後6か月位に決議のための債権者集会が招集される)
(可決の要件)
(1)議決権者の過半数の同意(頭数の要件)
(2)議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意(債権額の要件)
再生計画の認可(決議後1か月位)
・裁判所は不認可事由がないかを調査し、それが存在しなければ認可する(民事再生法第174条)。
・再生計画認可後は担保権が実行可能となる。
再生計画の遂行
計画による弁済の期間は、原則として最長10年(民事再生法第155条第3項)
再生計画の履行完了
5 会社更生について解説

<会社更生とは>
会社更生とは、株式会社の形態をとる企業が倒産の危機に瀕して(ひんして)はいるがまだ再建の可能性がある場合に,裁判所の監督の下,事業を継続しつつ再建をはかる手続です。会社更生法に基づいて、裁判所の選任した更生管財人の主導の下、手続きが進められます。
最終的には、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画が策定され、これを再生会社が遂行することにより事業の再建が図られます。
なお、会社更生を申し立てると、どこの銀行も貸してくれなくなるので、事業継続のための運転資金をまかなってくれる存在(=スポンサー企業)が不可欠といえるでしょう。
<民事再生との違い>
裁判所を通じて会社の再建を図るという点では、会社更生も民事再生も同じです。しかし、2つの手続きには以下のような違いがあります。
①会社更生は株式会社のみが利用できる。
民事再生は法人のほか個人も対象とされています。
②会社更生では現経営陣は退陣する。
会社更生では更生管財人が選任され、会社の経営や財産の管理・処分をする権利は全て管財人に移管されます。このため、それまでの経営陣は経営から退くことになります。そのため、一人株主や同族経営が多い中小企業にとっては使い勝手が悪く、どちらかというと大企業に適した手続きといえるでしょう。
③既存の株主は権利を失う
更生会社が債務超過状態にあるときは、株主は議決権を失うとされており、株主は手続きには全く関与できません。開始決定後の事業運営や更生計画(債権の減額・返済計画・新役員の選任等を主な内容とする)の作成はすべて管財人によって進められます。更生計画の認可後、同計画に従って債務の返済を行っていくのも管財人です。
スポンサー企業が資金協力(出資)した場合、同企業が株主となります。
④すべての権利が変更の対象となる
更生手続きの開始決定がでると、担保を持っていた債権者も含めすべての債権者が、今後定められる更生計画に拘束されます(つまりカットされる)。よって、開始決定後は担保権の実行はできません。
また、租税も更正手続に含まれ、手続が開始されると支払禁止となります。
よって、会社更生は民事再生と比べてより強力な手続と言えます。
⑤裁判所に納める費用(予納金)が高額
予納金の額は、会社の規模や債権者の数、債務の総額などの事情を考慮して決められますが、会社更生の場合、予納金は民事再生よりも高額になります。
会社更生は、担保権者や株主などすべての利害関係人を手続きに取り込んで拘束し、会社の役員、資本構成、組織変更までを含めた「抜本的な再建計画」の立案まで可能とするいわば「強力な手続き」といえます。その分、手続が複雑かつ厳格であるため、手続きおよび費用の負担が大きくなります。
<DIP型会社更生>
会社更生は、民事再生に比べ強力な手続であるため、会社の建て直しに有用といえます。
しかし、①現経営陣が原則として退陣する、②予納金などのコストが高い、③民事再生よりも時間がかかる、などの点から、その利用が避けられているとの現状があります。
そこで、経営陣が経営から退くことがなく、かつ、手続を迅速に終了することができる「DIP型会社更生」という手続が東京地裁で始まりました。
DIP型会社更生手続は、更生管財人を従来の経営陣から選び、経営をさせることによって事業を再建させるもので、原則として経営陣が退くという会社更生のデメリットを克服できるものとなっています。
ただし、現経営陣を更生管財人に選任するには、以下の要件が必要とされています。
(1)現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと
(2)主要な債権者が、現経営陣が経営に関与することに反対していないこと
(3)スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解を得ていること
(4)現経営陣が経営に関与することによって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められないこと
また、時間の短縮についても、東京地方裁判所では、更生手続開始の申立てから、更生計画の認可まで6ヶ月ほどで進行させる運用がなされており、従来に比べてかなりスピーディに手続きが進行することが予想されます。当然、これに連動して予納金の額も下がるはずですから、今後利用する会社が増えるものと考えられます
6 銀行債務のリスケ(リスケジュール)・新規融資
銀行債務のリスケとは、銀行と交渉して、一定期間返済を軽くしてもらう方法です。
あくまで一時的に資金繰りが厳しくなった場合の対処法であること、正常返済に戻るのに要する期間が半年程度であること、といった点に留意すべきです。また、専門家からアドバイスを受けることはできますが、銀行と直接交渉するのはあくまでも経営者です。
さらに注意すべき点としては、「再生専門家」と称する金融ブローカーに騙されないことです。金融ブローカーが交渉したところで、有利な条件でのリスケや新規融資が採れるほど甘くありません。結局、自分で交渉した場合と変わらない条件であるうえ、高額の手数料を取られるのでかえって高くつくことになります。
7 その他の制度
リスケや新規融資は多少の資金繰りに行き詰っているような場合の手法です。資金繰り深刻なほど悪化しているなら中小企業再生支援協議会・事業再生ADRなどの制度も選択肢となるでしょう。
<事業再生ADR>
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは裁判外の紛争処理手続のことをいいます。
経産省認定団体である事業再生実務家協会 (JATP)が、再生企業と銀行との間に入り、つなぎ融資や無担保債務の減免などを前提とした事業再生計画を取り決めます。
<中小企業再生支援協議会>
中小企業再生支援協議会とは、中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的機関」(経済産業省委託事業)です。経済産業大臣から認定を受けた商工会議所や商工会連合会などの認定支援機関に設置される公的組織です(47都道府県に設置)。
業再生に関する知識と経験を有する専門家(弁護士、金融機関出身者、公認会計士、税理士、中小企業診断士等)が常駐し、中小企業からの相談を受け付ける体制を整えています。
ヒアリングの結果、事業再生が可能と判断した場合、抜本的な財務体質や経営改善などを内容とする再生計画の策定を支援し、リスケジュールに向け、金融機関との調整を引き受けてくれます。
<民事再生や会社更生との違い>
根本的な違いは、民事再生や会社更生が裁判手続きであるのに対し、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会は裁判手続きではなく、あくまで金融機関との話し合いによる解決手法であるという点です。
民事再生や会社更生は裁判手続きであるため、多数債権者の承認があれば、強制的に債務が削減され、長期支払い計画を組むことができるというメリットがあります。半面、現在の取引先債権者の権利も変更対象となり取引先との関係悪化が懸念される、企業名が開示されるので企業価値が毀損される可能性があるといったデメリットがあります。
これに対し、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会は裁判手続きではないため秘密性が守られ、企業価値が毀損される可能性は低いといえます。ただし、これらはみな対象債権者の同意がないと再生計画が成立しないので、債権者(銀行等)に大きな負担を求めるような事業再生計画の実現は困難です。また、そもそも銀行が、経済的に行き詰った企業に債務免除をしたり、つなぎ融資をしたりするのかといった疑問もあります。現実には、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会など制度はあまり利用されていないとも言われているのはそのためでしょう。
会社の再生方法にはいろいろな制度や手法があるので,どの方法を使えばよいかについては,中立的な立場(債権者寄りではないという意味)にある弁護士に相談するのがよいでしょう。
8 会社分割による事業再生
巷には「別会社を使った事業再生」などを謳い文句にする事業再生コンサル業者が少なからずいます。これは、会社法上の企業分割制度を悪用して、資金難となった会社を企業分割し、もとの会社の重要な資産と債権者だけを新会社に移した後、借金だけとなったもとの会社を破産させるという方法です。
しかし、会社法の改正により、このような詐害的な会社分割は一定の要件を満たした場合には、もとの会社の債権者は新設会社に対し承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できるものとされました。
中には、問題のある会社分割という手法を勧めて高額な報酬を取ろうとするコンサル業者もいますので注意してください。よって、のような方法をとる場合には、法律の専門家である弁護士に相談するようにしてください。