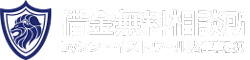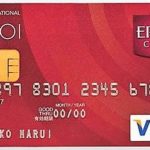今やテレビCMやネットで「過払い金請求」の広告を見ない日はないでよね。
自分にも過払い金があるのでは、と思っている方も多いでしょう。
過払い金とは、消費者金融(いわゆるサラ金)を利用していた人が法律の上限を超える利息を長期間払い続けたことによって発生した「払いすぎた利息」のこと。この支払い過ぎた利息を手元に取り戻すための手続が、過払い金返還請求です。
当初、貸金業者は、利息制限法を超過する利息の支払であっても、任意に支払った場合には本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が有効になると主張し、過払い金の支払には応じていませんでした。
しかし、平成18年1月13日、最高裁は、期限の利益喪失特約がある場合、特段の事情のない限り、制限超過部分の支払は、「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないと判示しました。貸金業者との契約には、返済を怠った場合には残額を一括で支払わなければならないという期限の利益喪失特約が例外なく定められています。そのため、この判決からすると、利息制限法を超過して支払った利息(過払い金)は返還すべきことになるのです。これを境に、弁護士や司法書士らがこぞって過払い金請求を始めたのです。
ところで、長期間、サラ金やクレジット会社などの消費者金融を利用していた人は少なくないでしょう。このような方は、とりあえず「自分にも過払い金があるかもしれない」と考えてよいわけです。貸金業者は2009年までは軒並み上限を超える金利をとっていましたから、それ以前に利用していた方は過払い金がでているはずです。
では、過払い金があるかどうかはどうやってしらべるのでしょうか。
手っ取り早いのは、「過払い金請求」とネットで検索して、ヒットした弁護士や司法書士の事務所に電話やメールをすることです。簡単なヒアリングの後、依頼すれば無料で過払い金を計算してくれます。
しかし、弁護士や司法書士に依頼して過払い金の回収手続きをすると、当然ですが費用がかかりますよね。
この費用がもったいないと考えるなら、自分で一人で過払い金の請求をすることも実は可能です。そこで、以下では、過払い金の請求を自分でやる場合の手順を説明していきます!
ステップ1:まずは貸金業者から取引履歴を取り寄せる
最初にやるべきことは過払い金の計算です。そもそも過払い金が出ているのか、いくら出ているのか、これらが分からなければ貸金業者に過払い金の返還を求めることもできません。
過払い金の計算をするのに欠かせないものが「取引履歴」です。
取引履歴とは、その貸金業者から「いつ、いくらお金を借りて」「いつ、いくらお金を返済したか」が記録された資料のことです。貸金業者は全顧客について取引履歴を保管しています。ただし、業者によっては一定時期以前の記録は保存していない場合があります(レイク、ニコス、エポスなど)。利用者が貸金業者に対して取引履歴を提出するよう求めることを「取引履歴の開示」「取引履歴開示請求」などと言います。
取引履歴の開示請求は、通常、貸金業者に電話するか、直接店舗に行けば、これに応じてくれます。取引履歴の受け取りには1週間~3カ月くらいの時間がかかりますが、郵送や店舗で受け取ることができます。また、貸金業者によっては取引履歴を取り寄せ費用(1000円ほど)をとるところもあります。
取引履歴をFAXや郵送で取り寄せる場合
取引履歴をFAXや郵送で取り寄せるには「取引履歴開示請求書」を作成し、これと一緒に本人確認資料(運転免許証やパスポートなどの写し)を貸金業者に送ります。
取引履歴開示請求書には以下のような事項を記載します。
・表題 「取引履歴開示請求書」と記載します。
・貸金業者名
・開示請求日
・氏名(その横に印鑑を押す)
・生年月日
・会員番号
・電話番号
・現住所(契約当時の住所が異なる場合はその住所)
・開示を求める文書
「貴社と私との金銭消費賃借契約に係る貸付当初より現在にいたるまでの取引経過の全部」と記載します。
・開示を求める理由
「貴社との取引における残高を確認するため」と記載します。
取引履歴の開示を請求した場合、貸金業者から電話があり、取引履歴を使う目的を聞かれることがあります。その際には、「過払い金請求をするため」では言わず、「取引の残高を確認するため」と答えるようにしてください。過払い金請求をするためと答えてしまうと、後日、過払い金の請求をした際、貸金業者から、その時点で「過払いになっている」と認識していながら返済をしていたと主張され、以後の過払い金の返還を拒否されることがあります。これは債務がないことを知りつつ、返済したお金については後日「返してほしい」と言えなくなるという規定(非債弁済:民法705条)があるからです。
ステップ2:過払い金を計算する(引き直し計算)
過払い金の計算は、取引履歴に記載された「借入や返済の各金額、その各日付」をもとに計算することができます。これを「引き直し計算」と言います。
引き直し計算とは、貸金業者との間で行われた貸付けや返済などのすべての取引について、利息制限法で定められた上限金利の利率に直して計算し、利息制限法に従っていたら借金の残高がいくらになるかを計算することです。
業者と契約したときの利率(約定利率)が利息制限法の上限利率を超えていた場合、引き直し計算によって算出される残高は実際の残高(約定残高)よりも少なくなるはずです。その場合、借入残高が0円になった後も返済を続けているので、それらは払わなくてもよいお金を払っていたことになります。この合計が過払い金なのです。
通常、引き直し計算は、専門のソフト(大半はエクセル)を利用すれば簡単に計算できます。ソフトの入手方法ですが、インターネットで無料の過払い金計算ソフトを探してダウンロードすればよいでしょう。
過払い金計算ソフトを入手したら、Excelの使えるパソコンを使って、所定のセルに借入金額、返済した金額、その各年月日を入力すれば、自動的に引き直し計算がされ、最終借入残高の欄に過払い金(元金)が表示されます(過払い金が発生しているときはマイナスの金額が表示されます)。
このように過払い金は自分一人でも計算することはできますが、入力ミスなどが1つでもあると過払い金額も間違った額になり、本来発生している額より少なくなってしまったり、逆に過剰になると貸金業者から拒否されることがあるので、細心の注意を払って正確に入力しましょう。
過払い金には元金と利息がある
引き直し計算ソフトへの入力が終わると、最終取引日の「借入残高」の欄に過払い金がマイナス数値で表示されます。これはその取引日時点で発生している過払い金(過払元金)です。
ところで、過払い金には遅延利息が付くことをご存知でしょうか。貸金業者は過払い金が発生しているのをわかっていながら、これを返還しなかったのですから、1種のペナルティとして、過払い金の発生時点から年5%の割合で遅延利息がつくのです(民法704条)。
通常、引き直し計算ソフトでは設定さえすれば、この利息も自動的に計算されます。各取引日の「利息」欄にはその時点までに発生した利息が積算されて表示されます。
よって、正確には「過払元金」と「過払い金利息」の合計が請求することができる過払い金ということになります。現在の裁判実務でも、この過払い金利息の請求は認められており、貸金業者も有効な反論ができませんから、ぜひ過払い金利息も漏れなく請求しましょう。
なお、利息制限法の上限金利は、借入額が10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下です。この上限金利を超える利息で返済をしていた場合に過払い金が発生します。
過払い金の時効に注意
すでに貸金業者との取引が終了している場合、過払い金は最終返済日から10年経過すると時効で消滅してしまいます。とくに、過払い金請求を自分でする場合、必要な書類の準備や引き直し計算に時間がかかったり、貸金業者から対応を後回しにされてたりして、時効をむかえてしまい、すべてが水の泡になってしまう可能性があります。
時効完成日は、最終返済日から10年経過日です。最終返済日は取引履歴に記載されているので、必ず確認しておきましょう。
ところで、貸金業者との契約は契約番号によって管理されており、契約番号が異なれば取引も別のものということになります。しかし、取引履歴を見ると、同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合があります。同じ契約番号の複数の取引を1つの取引として扱うのか、複数の取引を別個のものとして扱うのかについては注意が必要です。なぜなら、1つの取引として扱うなら引き直し計算も一連で行い、時効の起算日である最終取引日も1つということになりますが、これを別個の取引として扱うなら、引き直し計算も別々に行い、時効起算日も取引ごとに判断しなければならなくなるからです。
このような処理については、複雑ですが非常に重要な点ですから、過払い金請求に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
ステップ3:貸金業者に過払い金の返還請求をする
過払い金の額が計算できたら、いよいよ過払い金を返還するよう貸金業者に請求します。
請求の方法は、その旨を記載した「過払い金返還請求書」という書面を送付するだけです。
過払い金請求書には、以下の内容を記載します。
・表題 「過払い金返還請求書」と記載します。
・日付
・過払い金請求をする貸金業者名
・過払い金請求をする貸金業者の代表者氏名(会社の登記を見ましょう)
・自分の氏名
・契約番号や会員番号
・現住所
・連絡先電話番号
・振込口座名(金融機関名、支店名、預金の種類、名義人、口座番号)
・請求文言
「貴社との金銭消費貸借契約に基づく取引につき、利息制限法に基づいて引き直し計算した結果、○○円の過払い金(うち過払元金〇〇円)があることが判明したので、これを返還するよう請求する」などと記載します。
過払い金返還請求書は、貸金業者宛にファクシミリか郵便で送ればよいのですが、できれば内容証明郵便で送るべきです。内容証明で送る場合の送料は1500円前後です。
内容証明郵便とは「いつ・だれが・どこに、どのような内容の文書を送ったか」を証明できる郵便で、これにより貸金業者の「過払い金返還請求書は届いていない」といった主張を封じることができます。
また、過払い金の時効が近い場合には、過払い金の支払いを催告した事実の証明となるので、時効完成を暫定的に6カ月延長できるというメリットがあります。
時効が迫っている場合の緊急手段として「催告」という制度があります(民法153条)。催告とは「支払ってください」と促すことで、催告後6カ月以内に時効中断措置をとれば、時効完成日以後であっても時効中断の効力が認められるというものです。ただし、催告で時効を延長できるのは1回だけです。
ステップ4:貸金業者と過払い金返還についての交渉をする

過払い金返還請求書を送ると貸金業者から連絡があるので、過払い金の返還についての条件(金額、支払日、支払方法など)について話し合います。
ただし、自分で交渉する場合、以下の点を頭に入れておくべきです。
まず、相手は貸金業者で、ある意味「過払い金のプロ」。これに対し、あなたは素人です。法律の知識もあまりありません。次に、相手は、なるべく過払い金を払いたくない、というスタンス。あなたは過払い金の相場についての情報を持ち合わせていません。交渉が難航したとき、業者はあなたの請求を放置すればよいのですが(あわよくば、諦めるか、時効にかかってしまえばラッキーと思っている)、あなたには「伝家の宝刀」がありません。「伝家の宝刀」とは、裁判です。
具体的には、貸金業者から言われるがままに話をすすめないことです。貸金業者は、なるべく過払い金を払いたくないのですから、素人のあなたを言いくるめて、相場より相当低い金額で和解しようと交渉してきます。また、金額だけでなく支払方法についても、かなり先延ばしにされることもあります。
もし、自分で交渉してみて、貸金業者から和解金額や支払方法、支払時期について提案があったのなら、それに応じるのが妥当なのかについて、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてください。
貸金業者は過払い金利息を認めない
過払い金には利息がつくと説明しましたが、貸金業者は裁判外の交渉、とくに弁護士や司法書士ではない利用者個人が交渉した場合には、まずこの過払い金利息の支払を認めません。過払い金利息を認めないということは、引き直し計算においてその都度発生する過払い金利息を借入残高に充当しないで計算するため、充当した場合と比べて、過払元金自体も相当低くなることを意味します。
ゼロ和解に注意
いまだ返済途中の人が取引履歴の開示請求をすると、貸金業者から「お支払する過払い金はありませんが、代わりに残りの借金を0円にするので和解しませんか」とゼロ和解を提案されることがあります。このような提案を「ゼロ和解」と言います。
借入残高が何十万もあるような場合、それがなくなるならいい提案だとしてそのまま和解する方も少なくありません。
しかし、業者が借金を0円にしてもよいということは、借入残高を上回る過払い金が発生している可能性が高いと考えてよいでしょう。過払い金がいくら出ているかの計算もせずにそのような提案を検討するのは非常に危険です。よって、ゼロ和解はせずに取引履歴を取り寄せて過払い金を計算してください。
返済途中の人が過払い金の請求をした場合
法律理論からすれば、過払い金が発生しているなら借入残高が0円であることは明白なので、支払義務がないことになります。
ただし、返済途中の人が、自分で過払い金の請求をした場合、貸金業者からの支払督促が止まるわけではありません。督促が止まるのは弁護士や司法書士に過払い金の請求を依頼した時だけです。これは法律のプロである弁護士などが代理人となって、いわば盾になるので貸金業者も支払督促をしないからです。
過払いになっているのだからもう支払わなくてよいと勘違いをして、支払いをしなかった結果、延滞や滞納が原因でブラックリストにのってしまう場合もあるので注意してください。
ステップ5:過払い金請求の裁判をする
過払い金請求の裁判は、裁判外で話し合いで交渉し和解をする場合に比べ、手間と時間はかかりますが、裁判が交渉のときよりは高額で和解ができる可能が高いといえます。また、裁判官が公平な立場で、和解成立に尽力してくれるので、判決ではなく和解を念頭に置くのであれば、それほど時間がかかるものでもありません。
過払い金請求の裁判をする場合、訴状とその付属書類を裁判所に提出し、裁判の申立てをしなければなりません。請求しようとする過払い金(元金)が140万円以内なら、貸金業者(被告)の本店所在地を管轄する簡易裁判所に、140万円超えなら地方裁判所に提出します。
(過払い金請求の裁判で必要な書類)
・訴状 訴状とは、自らが求める判決の内容(被告は原告に対し〇〇万円を払え)とその根拠となる事実を記載します。訴状は正本と副本の2部必要です。
・引き直し計算書 過払い金の計算根拠として訴状に添付します。
・取引履歴 過払い金が発生していることを裏付ける証拠として提出します。
・証拠説明書 証拠の内容を説明した書面です。
・代表者事項証明書(登記簿謄本) 被告である貸金業者を証明する資料のことで、法務局で取得します。
・印紙 裁判を利用するにあたっての手数料です。請求額に応じた所定の金額の収入印紙を訴状に貼り付けます。
例えば、過払い金が40~50万円なら5000円、90~100万円なら10、000円、180~200万円なら18、000円の印紙を貼り付けます。
・予納郵券 訴状や主張書面などを被告に郵送する際に使用する切手のことで、訴えた側(原告)が所定の金額分を予納します。6000円位と考えておけばよいでしょう。
業者が裁判で主張する争点
裁判の申立後は、裁判が開かれる日(裁判期日)に裁判所に出廷して、主張と反論、そして立証という攻防を行います。裁判で自らの主張や反論をしたい場合には、それを法廷で述べるのではなく、裁判期日までにそれらの主張を記載した「準備書面」という書面を裁判所と相手方(被告)にそれぞれ提出します。この書面を期日で提出しないと主張したものとして取扱ってくれません。
過払い金請求の裁判では、貸金業者がよく主張してくる争点というものがあります。
このような争点は、貸金業者が、過払い金は発生していない、もしくは請求額よりも少ないと裁判所に認めてもらうために主張するものです。ですから、業者がどのような争点を主張してくるのかを理解し、それに対し有効な反論を用意しておかなければ、裁判所は業者の主張を認め、その結果、認められる過払い金が減額されたり、最悪の場合、過払い金を1円も取り戻せなくなったりすることもあります。
以下では、典型的は争点(業者の主張)の紹介をしておきます。
①悪意の受益者ではないとの主張
過払い金利息が発生する根拠は民法704条(悪意の受益者)です。簡単に言うと、過払い金は本来すぐに返還すべきものなのに、これを知りつつ返さなかったのだから、保有していた貸金業者は、その間の遅延利息を付して返還すべきだという規定です。
しかし、貸金業者は「みなし弁済」(旧貸金業法43条)を盾に、債務者が任意に利息を支払った場合には、本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下、有効になると主張してきます。また、旧貸金業法43条1項が成立しない場合でも、その適用があるとの認識を有し、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ない特段の事情があるので、民法704条の「悪意の受益者」ではないとも主張します。
これらの主張に対する反論としては、みなし弁済規定の要件を満たしていないことや業者のいう「特段の事情」は認められないことなどを具体的に主張していきます。
②空白期間による取引の分断
取引の分断とは、1つの契約番号の取引において、借主がいったん約定債務を完済した後、借入をしない空白期間を開けた後、あらためて取引を再開したような場合、空白期間前後の取引は別個の取引であるとする主張です。その主張の狙いは過払い金の消滅時効です。
つまり、空白期間の前後で取引が2つに分断されるなら(前の取引を第1取引、後の取引を第2取引とします)、いったん完済した時点から第1取引の消滅時効はスタートするので、その時点から10年経過していれば時効消滅したことになります。よって、第2取引についての過払い金しか認めれなくなります。
この主張に対する反論としては、空白期間の長短、契約書を巻き直したか否か、第1取引の契約書が返却されたか、第1取引で使用していたキャッシングカードが失効したか、完済後に業者から取引再開の勧誘があったか、第1取引と第2取引とで契約条件(利率、限度額など)が異なるか否かなどの事情をもとに、空白期間があっても「過払い金を新たな借入に充当しようという意思」は認められるので、1つの取引として引き直し計算するべきだと主張します。
③期限の利益喪失による遅延損害金の発生
貸金業者は、取引期間中に何度か遅延があったりすると、期限の利益の喪失があったので、その後の支払はすべて遅延損害金の利率で計算すべきだと主張していきます。貸金業者との契約書には、必ずと言っていいほど期限の利益喪失特約が含まれています。これは、約束した期日までに返済が行われなかった場合は、残りの借金を一括で支払わなければならないという約束のことです。
この特約に従って支払う遅延損害金については、遅延損害金利率で計算されるのですが、この遅延損害金利率は上限29.2%まで認められているため、期限の利益喪失後の返済分を引き直し計算しても過払い金が発生することが少ないのです。
しかし、実際には、貸金業者は遅延があったとしても、期限の利益を喪失したとして一括を請求することはせず、遅れた日数分の遅延損害金だけをとって取引を続けているのです。にもかかわらず、過払い金請求の裁判になると、一転して「期限の利益喪失後の返済は遅延損害金利率(29.2%)で計算すべきだ」と主張してくるのです。
このような業者の主張に対しては、「信義則違反」「期限の利益再度付与」などの主張で反論していくことになります。すなわち、業者は、期限の利益喪失後においても一括請求しないうえ、遅れた日数分の遅延損害金はとるものの、その後は通常の利息を取り続け、追加の貸付まで行っているなどの事情を取り上げて、これらの行動は、借主において「自分はまだ期限の利益を喪失していない」と誤信させるようなもので、今さら、期限の利益を喪失したと主張するのは契約当事者間のルール(信義誠実の原則)に反するものとして認められないと主張します(信義則違反)。
または、そのような業者の行動からすると、一旦喪失した期限の利益を再度付与したといえるので、いまだ期限の利益喪失していないと主張します(期限の利益再度付与)。
④貸付停止措置による消滅時効の進行
貸付停止措置とは、返済の遅れが頻繁にあった場合、貸金業者が、当面新たな借入をできないように内部で処理することです。あくまで業者内部の処理なので、この措置がとられても、利用者には連絡されません。ただ、ATMでキャッシングしようとしても借入ができず、返済だけしか受け付けてくれなくなります。
そもそも過払い金が生じる仕組みは、払いすぎた利息がその後に発生する新たな借入れに充当されるからで、その根拠は、判例上、「過払い金の充当合意」にあるとされています。
過払い金充当合意とは、リボ払いキャッシング契約の貸主と借主の間には、払い過ぎた利息があったとしても、取引が終了しない限り、即返還を求めず、以後に発生するであろう借入金に順次充当(相殺)しようという意思があるというものです。
そこで、貸金業者は、貸付停止措置によって借主は新たな借入をしないのだから、過払い金充当合意はその時点で消滅したはずだ、充当合意が消滅した時点から過払い金の消滅時効はカウントされるので、すでに時効であるなどと主張するのです。
反論としては、貸付停止措置はあくまで貸金業者の内部的な措置であって、それが借主に明確に告知されたわけではないので、そのような事情だけでは消滅時効は進行しないと主張していくことになります。
以上の争点は一部です。実際の裁判では、その他さまざまな争点を主張してくる業者もあります。しかし、貸金業者としても勝訴判決を求めているのではなく、本心では和解して終結したいのです。ただ、できるだけ支払う過払い金を少なくしたいだけです。ですから、難解な主張が出てきても、ある程度の反論をしておけば、最終的には和解が成立することの方が多いでしょう。今はインターネットの情報も充実しているので、あきらめずに反論していきましょう。
ただ、自分で過払い金請求をしようと進めてみたものの、思った以上に手間がかかったり、不明点や不安がでてきたりした場合には、相談が無料の弁護士や司法書士に相談しましょう。もし、信頼できそうなら、そのまま弁護士や司法書士に依頼して、過払い金請求の手続きの途中からやってもらうことも可能です。
訴訟上の和解
通常、過払い金返還請求の裁判は、貸金業者(被告)が判決を求める場合は少ないといえます。貸金業者は、さまざま争点を持ち出して少しでも認められる過払い金が少なくなるように主張と反論を続けますが、その一方で、和解提案というものをしてきます。しかも、この提案額は、裁判外で交渉していたときに比べ、高額になることが多いのです。
これは、貸金業者が判決ではなく、裁判上の和解を成立させて裁判を終結させたいからです。
裁判上の和解とは、判決によらず双方の合意した内容で裁判を終わらせる手続きのことです。
訴訟上の和解が成立すると「和解調書」が作成されます。和解調書は判決文と同様、被告(貸金業者)が和解した内容に違反した場合、これに基づいて強制執行をすることができるので、判決をもらったときと同様の強制力を期待できます。ただし、和解成立により裁判は終結するので、和解後に不満があっても控訴はできません。和解する際には、自分だけで判断すると危険なので、弁護士などの専門家に無料相談してみるのも手です。
他方、裁判外で業者と交わした和解書については、このような強制力はありません。
ステップ6:貸金業者からの過払い金が支払われる
訴訟上の和解が成立した場合、そこには業者が支払うべき過払い金(解決金)とその支払時期、振込先、期日に支払わなかった場合のペナルティなどが記載されます。裁判上の和解では、支払時期は1カ月~2カ月先に設定されることが一般的です。
過払い金請求を自分でする場合のデメリット・メリット
過払い金請求は、多くの人は弁護士や司法書士に依頼します。ただ、弁護士や司法書士に依頼すれば費用がかかります。もちろん、自分で過払い金請求の手続きすることも可能です。
ただ、自分で過払い金請求の手続きをやる場合には、メリットもある反面、デメリットも少なくありません。以下では、そのメリットとデメリットをまとめてみます。
<過払い金請求を自分でする場合のメリット>
一番は、専門家に依頼した場合にかかる費用を節約できるという点です。弁護士や司法書士に依頼すれば、事務所によってさまざまですが、相場的には回収した過払い金の18~25%ほどの成功報酬金がかかります。収入印紙代や郵券代、書類を取り寄せるための手数料などは必要最小限の費用は発生しますが、それを払えば、もどってきた過払い金は全部自分のものです。
その他のメリットとしては、「過払い金請求を全部自分でやった」という満足感です。
<過払い金請求を自分でする場合のデメリット>
1つ目は、過払い金がもどってくるまでの時間と労力がかかること
過払い金請求を自分でする場合、以下の書類をすべて自分で用意するので手間と時間がかかります。
・取引履歴
・引き直し計算書
・過払い金返還請求書
・内容証明郵便
・裁判をする場合は、訴状、証拠説明書、引き直し計算書、代表者事項証明書(登記簿謄本)、印紙、郵券
・裁判で提出する準備書面
また、過払い金の交渉や裁判には、ある程度の法律知識が必要でしょう。これらの知識・情報は書籍やインターネットで調べることはできますが、仕事の合間にこれらを行うのはかなりハードです。さらに裁判をした場合には、裁判は平日の日中に開かれるので、そのため仕事を休んで出廷しなければなりません。 これが何回か続くのです。
そして、取引履歴の取り寄せには約1週間~3ヵ月程度の時間がかかります。
しかし、貸金業者は弁護士や司法書士からの依頼を優先し、個人からの開示依頼については後回しにすることがあります。
取引履歴の取り寄せに時間がかかりすぎると、過払い金の請求自体も遅くなってしまいます。しかも、何か月も経って取引履歴が届いたときには、すでに最終返済日から10年が経過し、時効になっている場合も考えられます。中には、時効間近の取引についてあえて時効完成後に取引履歴を発送する悪質な業者もいます。時効が迫っているような場合は、その対処法に詳しい弁護士や司法書士に最初から依頼する方が安心です。
最近では、貸金業者も法定内利率での貸付けや総量規制などから以前に比べ収益が激減しています。にもかかわらず、未だに過払い金の返還は後を絶たないため、その財務的体力は相当疲弊しています。よって、時間が経てばたつほど、過払い金の返還率は低下し行くことが予想されます。実際、3年前と比較し、アコム、プロミス、レイク、アイフルなどの大手の会社でも、返還率が下がり、回収までにかかる時間は長くなっています。
せっかく自分で過払い金請求をやって弁護士費用を抑えても、結局、時間がかかって取り戻す過払い金が少ないのでは「時間がかかった分」の損をすることになります。
2つ目は、もどってくる過払い金が少なくなること
弁護士など法律のプロが交渉した場合と一般個人が交渉した場合とでは、その差は圧倒的であり、それは戻ってくる過払い金額にあらわれます。
その理由は、
・法律を含め、過払い金請求訴訟に関する裁判例の蓄積
・交渉の場数から習得した交渉に関するノウハウとスキル
・和解する場合の過払い金の相場(争点の有無によっていくら位が妥当なのか)を熟知
などが、弁護士などの専門家には備わっているからです。
また、過払い金利息を認めさせるかどうかで回収する過払い金に大差がでます。
前述したように、貸金業者は裁判外交渉では過払い金利息を認めません。過払い金利息を充当しないので過払元金自体も充当した場合に比べかなり低額になります。これに納得がいかなければ、自分で裁判をするしかないのです。過払い金請求に強い弁護士や司法書士に最初から依頼すれば、充当計算した過払い金を過払い金利息とともに90%以上の返還率で早期に取り戻してくれます。
もし貸金業者と交渉してあまりにも低額の過払い金を提案されたのであれば、その額が妥当なのか、どのくらいまで回収可能なのかについて、過払い金請求に強い弁護士や司法書士に無料相談してみることをお勧めします。
3つ目は、家族に知られる可能性が高いこと
過払い金を請求したことを家族に内緒にしておきたいと考える人は多いでしょう。もし分かってしまうと、借金をしていたことがバレる、もどってきた過払い金を自由に使えない、というのが主な理由でしょう。
でも、自分で過払い金請求をすると、裁判所や貸金業者からの連絡や書類がすべて自宅に届くので、家族に分かってしまうリスクが高くなります。
弁護士や司法書士に依頼すれば、貸金業者や裁判所からの連絡や書類の送付は、代理人である弁護士や司法書士事務所が窓口になって受けてもらえます。弁護士や司法書士から依頼者への連絡は携帯電話にしてもらい、事前に時間を指定しておくこともできます。郵送される書類も、個人名で送ったり、郵便局留めで送ったりするなど色々な配慮をしてもらえます。
まとめ
いかがでしたか。過払い金請求については、以上の手順を踏めば、自分でも手続きをすることが可能です。ただ、手続きにかかる費用だけでなく、返ってくる過払い金の額、かかる時間や労力なども総合的に考えて、自分で請求するかどうかを決めるのが良いでしょう。
この点、弁護士や司法書士などの専門家が存在するにはそれだけの理由があります。また、専門家に依頼して過払い金請求をする人の方が圧倒的に多いのも現実です。それは、やはり弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方が総合的に考えて「得する」からです。ここでの「得」は単にお金だけではないのです。
貸金業者と交渉中であっても和解が成立していなければ、途中からでも弁護士や司法書士が代理人として交渉することができます。(※140万円を超える過払い金については司法書士は扱えません)
シン・イストワール法律事務所でも、途中まで自分で過払い金請求を進めた方から相談を受け、その後、対応させていただいた例は多数あります。まずはお気軽にお問い合わせください。