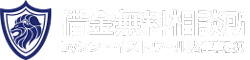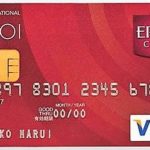自分で自己破産の手続きをするとはどういうことか
通常、自己破産の申立ては、弁護士や司法書士に依頼して行います。弁護士に依頼する場合は弁護士が「申立代理人」という立場で破産申立てから借金がなくなる(免責)までのすべての手続きを本人に代わって行ってくれます。他方、司法書士に依頼した場合は、「書類作成の代理」(破産申立書の作成を依頼する)なので、代理人による申立てではなく、借金をしているご本人による申立てとなります。
では、タイトルにもある自己破産申立書の作成も含め、すべて自分で自己破産の手続きを行う事は可能か、という質問ですが・・・
結論からいうと可能です。
実際、自分だけで自己破産の申立をしようという人は少ないと思いますが、やり方を聞かれることもありますので、その手順を説明していきたいと思います。
自己破産の手続きとは
自己破産の手続きとは、簡単にいうと、裁判所に自己破産の申立てをして、裁判所に借金の免責を認める決定をするよう求めることです。
具体的には、以下の点を書面に記載して裁判所の判断を仰ぐのです。
・自分にはこれだけの借金があり、今の収入や資産ではこれらを継続して返済していくことは困難であること
・自分の資産はこれだけであり、これを処分・換価して債権者に配当すること
・又は、自分には資産がないので債権者に配当はできないこと
・手持ちの資産を全て処分しても払いきれない借金については免責してほしいこと
・免責不許可事由(自己破産できない理由での借り入れ・浪費・FXでの借り入れなど)があるものの、これを反省しているので特別に免責を認めてほしいこと
以上のことを記載した書面を作成し、これを裁判所に提出します。書面の形式については、裁判所ごとにひな形(書式)を指定しているので、自分の住所を管轄する地方裁判所に問い合わせするか、ホームページなどをご覧いただいて、入手するようにしてください。
また、破産事件に詳しい弁護士や司法書士は裁判所ごとのひな形を持っていますから、無料相談などを活用してみるとよいでしょう。
自己破産の申立て準備
申立の準備としては、次の資料を作成し、収集します。
①破産・免責申立書
裁判所が指定した申立書のひな形があるので、これに氏名・生年月日、現住所・本籍地・電話番号などを記入します。
(添付する資料)住民票、戸籍謄本(東京地方裁判所では不要です)
②債権者一覧表・・・借金の額やその債権者を記載した一覧表のこと
(収集する資料)
・債権者(借入先)の債権届出 ⇒債権届出とは現在の債務額を記載した書面のことで、各債権者に連絡して書面を提出してもらいます。
(注意点)
・すべての借金を記載する=債権者の漏れがないようにしましょう。自己破産の免責は、債権一覧表に記載した債務額についてなされるものなので、もし漏れがあればその債務は免責されないまま残ってしまうことになるので注意が必要です。
・取引が平成19年以前から始まっている貸金業者については、法律の上限利率を超えた利息を取っている可能性が高いので、法定利率に引き直して計算をした債務額を記載する必要があります。もし、これを自分でやるのなら、引き直し計算ソフトとパソコンが不可欠でしょう。
・また、「原債権者」と「現在の債権者」を明確に区別して記載しましょう。例えば、A銀行からの借入があり、返済が滞ったためB保証会社がその銀行に対して代位弁済した場合には、そのB保証会社が債務者に対して求償権を取得するので、現在の債権者はB保証会社です。元々の債権者であるA銀行は「原債権者」と表記します。さらに、B保証会社が、債権回収をC社に委託した場合、C社から支払督促がくることになりますが、あくまで現在の債権者はB保証会社です。
債権者一覧表は、債権届出をもとに作成することはできますが、債権届出は、法的な知識がないと内容が理解できないことが多く、債権者ごとに郵便等で取り寄せをする必要があるので、相当手間もかかります。
③資産目録・・・資産に関する一覧表のこと
申立時点における以下の資産についてリストを作り、それに関連する資料(すべて写しで可)を添付します。
| 資産 | 添付資料(収集資料) |
| 20万円以上の現金や預貯金 (東京地方裁判所では33万円以上の現金) | 金融機関の通帳(過去2年分の全ページの写し) 自身の名義の口座はすべて対象となる。通帳の記載で20万円を超える金額の出入りがあった場合にはその内容を説明する必要がある。 |
| 公的扶助の受給額 (生活保護、年金、児童手当等) | 受給証明書 |
| 報酬・賃金 | 直近3ヶ月分の給与明細書 源泉徴収票、自営なら確定申告書 ※無収入なら課税証明書 |
| 退職金 ※在職中の場合は、現在、退職職したと仮定して算出する退職金 | 退職金見込み額証明書(在職中の場合) 退職金明細書(退職した場合) ※退職金の見込み額の1/8が20万円以上の場合には資産とみなされます。 |
| 保険(生命保険、損害保険、火災保険、自動車保険など) | 保険証書、解約返戻金計算書 |
| 貸付金、売掛金 | 借用書、発注書、請求書 |
| 積立金 (社内積立金、財形貯蓄など) | 積立金等の残高報告書 |
| 有価証券(株式・社債など) | 有価証券の証書、時価のわかる資料 |
| 自動車、バイク | 査定資料、車検証 |
| 過去5年間に購入したもので購入価格が20万円以上の物 | 査定資料など |
| 過去2年間に処分した財産で評価額または処分額が20万円以上の物 (例)不動産や自動車を売却したことにより20万円以上の現金を取得した場合、生命保険を解約した結果、20万円以上の解約返戻金を受領した場合 | 売買契約書、解約返戻金明細書など |
| 不動産 (土地、建物、マンション) ※住宅ローン残高が不動産の査定額の1.5倍以上なら対象外です。 | 登記簿謄本、固定資産税評価証明書 住宅ローン契約書、償還計画表 |
| 相続財産 (遺産分割未了の場合も含む) | 財産の内容が分かる資料、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本 |
④陳述書・・・直近10年の仕事内容や現在の生活状況、借入れ原因及び破産に至った事情、免責不許可事由がある場合はその詳細などについて記述します(ひな形の書式に沿って記載すればよい)。
⑤家計表・・・申立直前2ヶ月分の家計表(収入と支出の明細のこと)
ひな形があるので実際の金額を記入しましょう。
裁判所へ自己破産の申立てをする
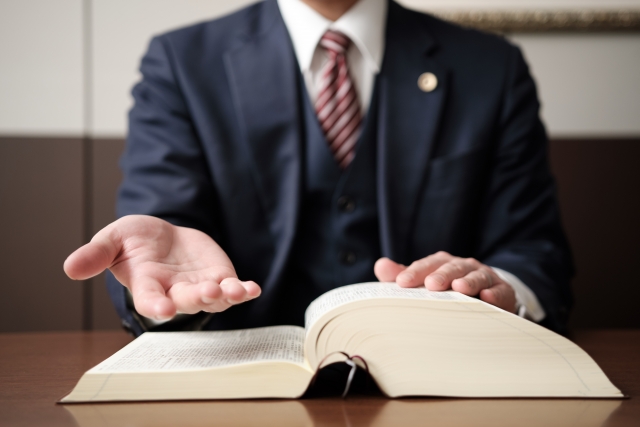
前記で作成・収集した書類と資料を1つにまとめて、地方裁判所(破産部)に提出します。なお、申立書には相当額の印紙を貼り、所定額の郵券を添えます。
※東京地方裁判所では、印紙1500円、郵券代4200円です。
裁判所から連絡がくる「破産審尋」
自己破産の申立てが受理されると、裁判所は申立人(弁護士が申立てをした場合は代理人弁護士)を裁判所に呼び出し、破産の審尋を行います。破産審尋とは、破産手続きを開始するかどうかを決定するために、裁判官が、呼び出した申立人に対し事情を聴取したり質問したりすることです。訊かれる内容は、資産のことや破産に至る経緯などで、審尋の時間は10分から15分ほどです。
破産審尋は平日の日中に裁判所から指定された時間に裁判所に出廷して行うので、もし自分で自己破産の申立てを行う場合には、仕事を休む必要があります。
一方、弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合には、法律の専門家である弁護士が負債や資産・収入について十分調査しているとみなされるので、破産審尋自体を省略する裁判所が多いと言えます。仮に破産審尋が実施される場合でも、申立代理人である弁護士が裁判所に出廷するので、本人が出廷する必要はないのです。
審尋の結果、裁判官は問題がなければ破産手続きの開始を決定します。このとき、破産の手続きを管財事件とするか同時廃止事件とするかについても決定します。
管財事件と同時廃止事件の違いについては下記で解説します。
後日、破産開始の決定がされた旨が記載された書類が郵送されてきます。この書類には破産事件の「事件番号」が記載されているので、以後、本件申立てはこの事件番号で呼ばれることになります。
破産開始決定後は、申立人は破産者となり、その旨が官報に掲載されます。よって、破産開始決定がでたら、官報公告をするための費用(1.2~1.9万円)を裁判所に納める必要があります。
自己破産の種類「管財事件」と「同時廃止事件」とは?
自己破産の手続きは、厳密には「破産手続き」と「免責手続き」の2つのパートに分かれます。「破産手続き」とは債務者の資産を換価してこれを債権者へ配当をする手続きのことです。「免責手続き」とは残った借金について支払義務を免責する手続きのことです。
また、破産の開始が決定されると、その破産事件は2つのコースに区分けされて処理されます。管財事件と同時廃止事件です。申し立てられた破産事件は必ずこのどちらかに振り分けられて進められます。
管財事件とは、基本的には換価すべき資産がある場合のコースで、これが原則形です。他方、同時廃止事件は換価すべき資産がない場合のコースで、いわば簡易な手続きです。その振り分け基準は次のとおりです。
| 管財事件 | 申立時点で20万円以上の資産を保有している場合、もしくは借金の原因に浪費、投資、ギャンブルがあるなど免責不許可事由がある場合 |
| 同時廃止事件 | 申立時点で20万円以上の資産を保有していない場合、かつ借金の原因に浪費、投資、ギャンブルがあるなど免責不許可事由がない場合 |
それでは、それぞれのコースで、「破産手続き」と「免責手続き」はどのように進展するのでしょうか。下の表にまとめました。
| 管財事件 | 同時廃止事件 | |
| 破産手続き (資産の処分・換価・配当手続き) | 管財人が選任され、管財人が破産手続きを行う | 換価すべき資産がないので、破産手続きは破産開始と同時に廃止される。 よって、管財人は選任されない。 |
| 免責手続き (借金免責の判断) | 管財人が免責すべきかどうかについて調査し、その意見を聞いて裁判所が判断する。 | 裁判所が事情を総合的に考慮して判断する。 |
管財事件となるか、同時廃止事件となるかで、以下のような違いがでてくるので重要です。
①破産管財人の選任と管財予納金
管財事件では破産管財人が選任され、以後、管財人が申立人の資産の換価・配当手続きや免責に関する調査を行います。管財人は弁護士の中から選任され、債権者の利益代理人というような立場で破産事件に関与します。
②管財事件では、管財予納金(後記7参照)として最低20万円が必要です。管財予納金は申立て後速やかに裁判所に納めなければなりません(ほとんどの裁判所が一括納付です)。
③破産管財人の調査
管財人はその職務を遂行するにあたり、申立人に直接質問したり、資料などの提出を求めたりすることができます。法律上、破産者は債権者らに対し説明義務が負っているため、破産管財人の調査を拒否することはできません。
また、管財人の調査を実効的なものにするために、破産申立後、申立人宛の郵便物はすべて管財人に転送されることになります。申立人が引っ越しや宿泊を伴う旅行をする場合でも管財人の許可をとる必要があります。
④終結までにかかる時間
同時廃止事件に比べ管財事件の方が終結までに時間がかかります。これは管財人による資産の処分・換価の手続きや免責に関する調査にその分時間がかかるからです。
予納金の納付
破産開始決定が出ると、裁判所が破産事件を処理するための費用を納めなくてはなりません。ただし、同時廃止事件については開始と同時に破産手続きが廃止(終了)されるため費用の納付は不要です。つまり、この費用は管財事件の場合だけかかるものなので「管財予納金」と言います。
管財予納金は最低50万円です。しかし、弁護士に破産の申立を依頼し、弁護士が申立代理人になった場合には最低20万円でよいとされています(この場合を「少額管財事件」と言います)。よって、自分で申立てをした場合(司法書士に依頼した場合も本人申立てに変わりありません)には、50万円管財予納金を用意する必要がありますが、弁護士に申立ての依頼をすると20万円で済むのです。これは、弁護士が申立代理人となっていれば、法律の専門家による事前の資産調査等が十分なされているものと信用できるため、その分、費用を割り引いたのです。
ですから、自己破産を自分でやる場合には、管財事件となりそうなときは予め50万円を用意しておく必要があるので注意してください。
追加予納金とは(財団組み入れ)
管財事件の場合、申立て後、速やかに予納金20万円を納めることになりますが、申立時点で20万円以上の資産がある場合にはその資産の換価分を破産財団に組み入れなければなりません。これを追加予納金といいます。ただ、破産申立て後の生活費を賄ううえで必要な場合は、99万円の範囲内であれば、裁判所に対し、財団組み入れをしないよう(つまり、そのまま保有できるよう)申し出ることができます。これを自由財産拡張の申入れといいます。
免責審尋
破産手続が終了するとその後は免責手続に入ります。免責審尋とは、裁判所が免責を許可してもよいかどうかを調査するための審尋(法廷での裁判官によるヒアリング)のことです。
大都市の裁判所などでは、大法廷に破産者を数十人ほど集めてまとめて行うこともあります(集団免責審尋)。
免責の決定
免責審尋が終了した後、債権者の異議などを参考にしながら、1週間から10日位で、裁判所が免責に関する決定をします。
弁護士に依頼して破産の申立てを行った場合、免責不許可事由に該当するようなケースでも、よほどのことがない限り免責は認められます。
免責が決定となると、免責決定の通知書が送られてきます。そして免責決定がされた旨が官報に公告されます。
自己破産の場合、官報に名前が掲載されるのは、破産手続開始決定後と免責許可決定後の2回です。その後2週間は、利害関係者が不服申立てをすることができます。何もなければ官報に掲載された翌日から2週間経過すると免責が確定します。
この時点で借金がゼロになるのです。
破産手続きを自分で行った場合と弁護士に依頼した場合とで費用はどう違うか
比較すると、以下のようになります。
| 自分でやる場合 (本人申立) | 司法書士に依頼する場合 (本人申立) | 弁護士に依頼する場合 (代理人申立) | |
| 申立時の印紙代 | 1500円 | 1500円 | 1500円 |
| 申立時の郵券代 | 4200円 | 4200円 | 4200円 |
| 官報広告費 | (同時廃止事件) 約1.2万円 (管財事件) 約1.9万円 | (同時廃止事件) 約1.2万円 (管財事件) 約1.9万円 | (同時廃止事件) 約1.2万円 (管財事件) 約1.9万円 |
| 管財予納金 (管財事件の場合) | 最低50万円 | 最低50万円 | 最低20万円 |
| 申立を専門家に依頼する費用 | 0円 | 30~50万円 ※事務所ごとに異なる | 30~50万円 ※事務所ごとに異なる |
| 評価 | 専門家に依頼する費用は0円 (もっとも安上がり) 但し、すべて自分でやる。 | 最もお金がかかる 司法書士は代理人ではないので全て任せることはできない。 | 自分でやるよりもお金はかかるが、すべて任せられる。 |
※裁判所によっては、上記の金額と若干異なる場合がありますので、裁判所ごとに確認してください。
自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット
自己破産の手続きを自分で全部やった場合、専門家に依頼する費用がかからないので、その分費用を抑えることができます。
しかし、自分ですべてやるとすると、資料の収集と作成にかかる時間と労力は半端なく大変です。仕事をしている人であれば、仕事の合間をみてこれらの作業にとりかかる必要があります。そのうえ、破産審尋などへの出廷のため仕事を休まなくてはなりません。また、法律的知識を欠くため、裁判所からの質問や資料の追加提出に的確に対応することができません。また、弁護士などの専門家が申し立てれば同時廃止事件ですむような案件も、自分だけでやったため、知識不足から管財事件として処理されてしまうといったケースもあります。
とくに管財事件の場合には、弁護士に依頼すれば、本人申立てに比べ、管財予納金が30万円も低く抑えられるという点です。この場合、仮に弁護士費用が30~40万円かかったとしても、手出しは0円か10万円ほど。その分、うっとうしい作業はすべて弁護士に任せることができるのです。
まとめ
いかがでしたか。費用を抑えるために、自己破産手続きを自分でやりたいと思われる方は多いかもしれません。でも、必ずしも安上がりになるとは限りません。また、貴方の時間や労力もお金に換算して比較するべきです。 医者、弁護士など専門家がいるにはそれなりの理由があるのです。