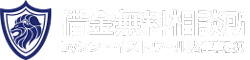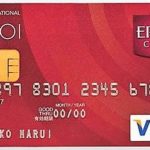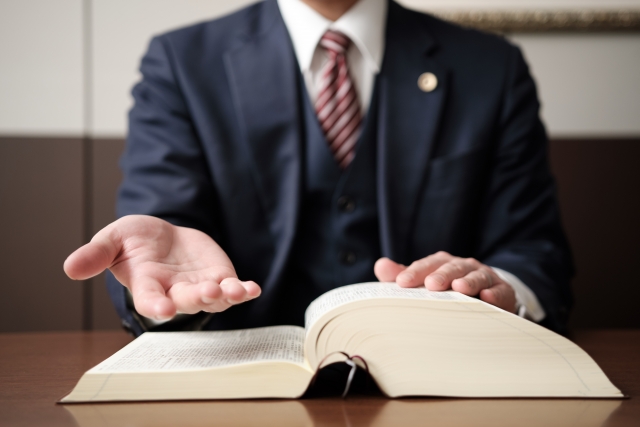
1.現在の養育費受給の状況
日本の養育費受給の実情は非常に深刻です。
厚労省による平成28年の全国母子世帯等調査の結果によると、母子世帯のうち60%以上の家庭では養育費の取り決めをしていません。また、取り決めのみならず、実際に支払ってもらっているかどうか、養育費の受給状況についても、養育費の支払いを受けていた母子世帯のうち40%は途中で支払われなくっているとのことでした。
上記結果では,養育費の取り決めをしていない母子世帯も多いのですが、養育費を月いくらにするかという取り決め自体はそんなに難しいことではありません。離婚時に協議すればよく、それが難しい場合でも弁護士に依頼したり、家庭裁判所に養育費支払に係る調停・審判を申立てれば、取り決め自体は簡単です。
問題は実際に支払ってもらう「回収」です。上記統計結果では取り決めをしても、そのうち4割近くが途中で支払を受けなくなっています。この背景には回収の難しさが起因します。
2.支払が途中で止まった場合どうするか
通常、養育費の取り決めは,次のいずれかによって成立します。
- 単なる口約束
- 私的文書(当事者が作成した合意書)
- 公正証書(公証役場が作成したもの)※強制執行認諾文言付きのもの
- 家事調停調書(調停によって合意が成立した場合)
- 家事審判書(審判によって支払命令がでた場合)
上記のいずれかによって支払合意が成立し、その通り養育費が支払われているうちはよいのですが、もし途中で支払われなくなった場合には、強制執行という方法で強制的に回収するしかありません。強制執行とは、国が強制的に債務者の財産から債権の回収を行ってくれる制度のことで、裁判所に執行の申立てをすることで利用できます。
しかし、強制執行をするには、「債務名義」というものが必要です。債務名義とは、その人の債権(養育費支払請求権)が実際に存在することを公的機関が認める文書のことで、典型的なものが裁判で勝った時の判決文です。上記の中では下の3つが債務名義に該当します。
よって、上2つで取り決めをしたケースでは、あらためて下の3ついずれかを取得する必要が出てくるのです。
3.強制執行の難しさ
ほとんどの弁護士は養育費の取り決めには関わってくれますが、その後の養育費の支払や未納養育費の回収をしてくれる弁護士は少ないと思います。
それはなぜでしょうか。それは強制的に取り立てることが現実には難しいからです。
先ほど説明したように債務名義があれば強制執行の申立ては可能なのですが、実はそれだけでは足りません。強制執行をするには、相手方(債務者)の財産を特定することが必要です。強制執行の申立ては具体的に「これこれこの様な場所にこの様な財産があるので、これを強制的に取り立ててください」
と裁判所にお願いすることです。執行裁判所は、申立てによって特定された財産を差し押さえて、そこから強制的にお金を回収してくれるのです。
財産の典型としては、銀行口座の預貯金、会社からの給料、不動産などがあります。
これらの財産に対し強制執行をするには、預貯金であればその債務者名義の銀行口座を特定(銀行名,支店名)する必要があります。給料であれば勤務先の特定が必要です。また,不動産であればその登記簿が必要となります。
しかし現実には、債権者は、債務者の財産については知らない(特定できるほどの情報がない)場合の方が多く、それを調査する有効な手段もほとんどありませんでした。
そのため、債務名義があっても、現実に回収することができず、泣き寝入りをするしかないというケースは多くありました。
4.2020年4月、民事執行法の改正
以上のように強制執行には財産を特定するという大きな壁があり、制度としても使い勝手が悪かったのですが、民事執行法の改正(2020.4.1施行)により、債務者の財産特定がし易くなりました。要するに、今回の改正により債務者の財産に関する情報を取得する方法が新設されたのです
具体的には、以下の4点が挙げられます。
①預貯金に関する情報取得の手続き
②給与債権に関する情報取得の手続き
③不動産に関する情報取得の手続き
④財産開示手続きの見直し
5.預貯金に関する情報取得

銀行等の金融機関から預金に関する情報を取得する手続が新設されました。
この手続きにより金融機関から、預貯金の有無、預貯金の残高、店舗名、口座番号等の情報を得ることができるようになりました。これらの情報をもとに判明した預貯金債権に対して強制執行をすることになります。
ただし、どの金融機関の情報の開示を求めるのかについては、申立人で特定する必要があります。不明な場合には、保有しているだろうという予測のもとに行うことになります。
6.給与債権に関する情報取得
裁判所を通じて、市町村などの公的機関から債務者の給与の支払先に関する情情報を取得する手続です。市町村や年金事務所は、給与支払者に関する情報を保有しており、債務者がどこから給与の支払を受けているか、つまり勤務先を把握しているからです。
ただし、勤務先に関する情報は高度なプライバシー情報であるため、養育費を請求する権利や、交通事故による損害賠償請求権など、限られた債権についてのみ申立てが認められています。
7.不動産に関する情報取得
これは、裁判所を通じて登記所から不動産に関する情報を取得する手続です。
これにより、債務者が所有者となっている土地や建物に関する情報を取得できるので、明らかになった不動産に対して強制執行(差し押さえて競売にかけ、その代金から回収する)をすることが可能です。
8.財産開示手続きの見直し
財産開示手続きとは、債務者を裁判所に呼び出して、債務者自身に財産内容を申告させるという制度です。
従来も、民事執行法には財産開示手続という制度があったのですが、手続き違反に対する罰則も軽かったことから(30万円以下の過料)出頭しない債務者も多く、実効性がないとの理由であまり利用されていませんでした。
そこで、今回の改正では実効性を担保するために手続き違反に対する罰則が強化されることになりました。裁判所からの呼び出しに応じなかったり、財産内容について陳述を拒否したり虚偽の陳述をしたりした場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰を科すことになったのです。
9.まとめ
以上のような民事執行法の改正によって、今後,泣き寝入りする債権者は少なくなると考えられます。特に、養育費の未払い等で困っているシングルマザーにとっては朗報と言えるでしょう。
ただ,①預貯金に関する情報取得手続き,②給与債権に関する情報取得手続き,③不動産に関する情報取得手続き,④財産開示手続きを行うには,各手続きに必要な資料の選別と収集が不可欠ですし,各申立てについての要件の吟味,申立書及び財産調査結果報告書等の作成などは一般の人が自分で行うにはかなりハードルが高いといえます。できれば,強制執行に詳しい弁護士事務所に相談することが望ましいでしょう。