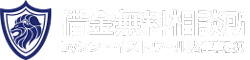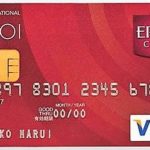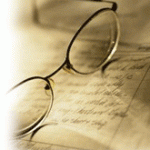任意整理をした後の生活について
任意整理は貸金業者との取引を清算し、合意によって取り決めた和解金を分割で弁済していく手続きです。和解金の弁済は原則として将来利息がカットされるので、これまでより支払はスムーズになるはず。支払えば支払った分だけ借金が減るからです。
お手続きを悩まれているお客様の多くは手続きした後、どの様に生活が待っているのか、支払いが滞ってしまった場合どうするのか、など質問されることがおおいです。任意整理をした後の生活については注意すべき点もあるので、債務整理に精通した弁護士が解説します。
まず信用情報機関に登録される
債務整理をするとその情報が信用情報機関に登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。登録機関は5年~10年といわれており、この期間中は、基本的に新規の借り入れができなくなり、今あるクレジットカードも使えなくなります。
具体的には、次のようなことが予想されます。
・消費者金融や銀行カードローンの新規申込ができなくなる
・新たにクレジットカードを作れなくなる
・すでにあるクレジットカードは更新されず、使えなくなる
・ローンが組めなくなる
・債権者が銀行の場合、その銀行の口座は使用できなくなる
・スマホ本体の分割払いができなくなる
・賃貸物件に入居する際、家賃保証会社を利用する場合にはその審査に落ちることがある
・子供が奨学金を借りる場合、保証人になれない
よって、任意整理をした後は、キャッシングができず、クレジット決済も難しくなるので、現金で決済をする必要があります。
ここに大きくネガティブな反応を示す方が多いです。ブラックリストに載ります、と言われて喜ぶ人はいません。ただ、それまでの借入に頼った生活に比べれば、かなり不便になるかもしれませんが、そもそも借金は貯金ではなく、負債なので、新たな借金を作らず、収入の範囲で生活をする習慣が(強制的に)身につけることが重要で、それに慣れていけば健全な生活を送ることができます。
毎月の支払の確保が必須
任意整理をすると、貸金業者らとの間で和解金を毎月分割で弁済するという合意が成立します(和解契約と言います)。弁済期間は、3~5年と長期にわたるので、その間、不履行なく支払が確保できるよう家計の管理が重要です。
注意すべきは、新たな借入をしないことです。任意整理の場合、複数の借入先のうち、一部の業者を選んで整理できるメリットがあるため、弁護士が介入しなかった業者については基本的に従来どおりの取引(借入と返済)が可能です。だからと言って、和解金の弁済をするために、介入しなかった業者から借入をするのは絶対NGです。新たな借入をすれば、その分返済も増えていくので、そのうち、介入整理した業者の和解金も支払もできなくなります。よって、1社でも任意整理をした場合には、「新たな借入は絶対しない」と肝に銘じることです。
毎月の支払が滞ったらどうなるのか?
では、任意整理をして和解金を弁済していく途中で、弁済が滞った場合、どうなるのでしょうか。
通常、和解契約には「期限の利益喪失」という約定が含まれています。これは和解金を毎月分割で弁済するけれど、1回でも(場合によっては2回)約束した期限に決められた和解金を支払わなかったときは、残額を一括で支払わなければならないという約束です。
これによって債権者が一括請求をしてきた場合、一括で支払える人はまずいないでしょう。支払がない場合、債権者は裁判を提起し、判決を取って強制的に取りにきます。強制執行というものです。サラリーマンの場合、給与の差し押さえが始まることになり、収入の一部を毎月強制的に徴収されるので、生活は困窮します。あとは自己破産の途しかなくなるでしょう。
建前としては、このような最悪のシナリオを避けるために、家計を節約して、和解金の支払を確保する努力をしていきましょう、というしかありません。
ただし、支払いが滞った場合でも、任意整理を依頼した弁護士や司法書士に頼めば、再度、間に入ってくれて再和解の合意をしてくれることが多いので、困ったときはすぐ相談しましょう。
支払が困難になったらどうすればよいか
でも、やむを得ない事情で和解金の弁済ができなくなるケースも少なくないでしょう。
例えば、
・リストラで職を失った
・会社の都合で給料が減額となった
・病気で入院し働けなくなった
・妻の収入がなくなった結果、家計が厳しくなった
このような場合は、当初の計画と大きく事情が変わるので、もはや和解契約をそのとおり履行していくことは不可能です。ひとりで悩まず、債務整理に詳しい弁護士に早めに相談して、「方向性」を決めることが重要です。
方向性とは、その業者について再度任意整理をするのか、それとも自己破産や個人再生をするのかということです。
もし一定期間支払を猶予してもらえれば支払えるようになるような場合、例えば、病気が治って退院すれば収入が元に戻るとか、再就職すれば従前と同様の収入が確保されるといった場合には、その業者について再度任意整理をすることをお勧めします。
これはもう一度、弁護士や司法書士が介入して、和解契約を成立させることです。弁護士などの介入によって、事実上、支払が猶予されるのである意味時間稼ぎができます。その間に今の問題を解決しようというのです。
他方、もう収入が元に戻りそうもないという場合には、自己破産をした方が得策でしょう。住宅ローンの支払だけは続けていきたいのであれば、個人再生を選択するとよいでしょう。いずれにしても、ひとりで悩まず弁護士や司法書士などの専門家に相談することです。借金の額、住宅、車、生命保険、退職金などの資産状況によって債務整理の内容も違ってきますが、その判断は債務整理に精通した弁護士や司法書士に任せるべきでしょう。
個人再生をした後の生活はどうなるの?

個人再生は自己破産と違って、債務を支払っていく方向の整理です。つまり、大幅に圧縮した借金を3年から5年で弁済するという計画(再生計画)を裁判所に認可してもらい、それを実行していくものです。個人再生では、今保有している財産を処分しなくてもよく、免責不許可事由なども不問です。これらはみな個人再生が、あくまでも返済を前提とするからです。
支払確保が最優先
個人再生の手続きにおいては、裁判所や民事再生委員は、申立人の家計の状況や支払能力を厳しくチェックし、履行テストといった制度も課せられます。
※履行テストとは、個人再生申立て後、再生計画認可前に、申立人に最低弁済額を4~6カ月間にわたって積み立てさせて、その弁済能力をテストする制度のこと
このようにして支払能力を厳しくチェックされてはじめて個人再生手続きが認められるのですから、再生計画がスタートした後の生活は、いかに弁済計画を着実に実行していくかに尽きるといえます。
個人再生手続きについて注意すべきポイント
先ほど話したように、個人再生後の生活では支払能力の確保が第1目標です。ところが、すべてが順調に進むとは限らないのが世の常です。
そこで、個人再生による弁済実行の障害となりそうなものを以下に紹介しておきますので、事前に予測し手立てを考えておくことが大切です。
・リストラによる失職
⇒収入がなくなれば、個人再生計画実行は不可能ですから、すぐに就職活動に着手してください。求職期間中は収入がありませんが、弁済自体は続ける必要があるので、貯金を取り崩したり、雇用保険給付を充てるなどして何とか弁済は続けていきましょう。
・傷病による休職
⇒社会保険に加入している場合、休職期間中に傷病手当が支給されるのでこれを原資に支払を継続しましょう。もっとも病状の経過を見ながら、復帰の目途がつかないようなら破産も視野に入れる必要がありますから、早期のうちに弁護士に相談しましょう。
・収入の減少
⇒収入減少には色々なことで起こり得ます。転職により給料が下がった、役職や業務内容が変わったことにより減収した、残業代が付かなくなったので手取りが少なくなったなどさまざまです。収入減少が一時的ではないものであれば、やはり早期のうちに、このまま個人再生をつづけるべきかどうかについて弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
・家計支出の増加
⇒個人再生を申立てた当時と比べて家計の支出が予想外に増加したような場合には、返済原資が足りなくなって、やはり個人再生計画の実行が困難になります。例えば、子供が産まれた、長男が大学に進学するといった事情でこれまでよりも支出が増えることがあります。このようなことは事前にある程度予想できることなので、予め対策を講じておくことが必要です。
個人再生をした後に支払いが遅れた場合どうなるのか
・再生計画の取り消し
個人再生の再生計画(弁済計画)は、確実に実行されることを前提としています。ですから、途中で弁済が遅れたりして計画が実行されない場合、つまり「再生計画の不履行」があるときには、裁判所によって再生計画自体が取り消されることになります。
再生計画が取り消された場合、すべての借金は再生計画認可前の金額(ただし再生計画で弁済した額を控除する)に戻ってしまうので、これまでの労力がすべて無駄となってしまいます。
ただ、1回遅れただけで再生計画が取り消されることは、めったにありません。
なぜなら、再生計画の取り消しは、再生債権者の申立てが必要だからです(申立てもなく裁判所が勝手に判断することはありません。)。しかも、総債権額の10分の1以上を占める債権者だけしか取り消しの申立てをすることができません。
また、債権者としても再生計画が取り消されても残額の回収ができるわけでもなく、弁済の遅れが解消するなら、そのまま計画どおり弁済してもらった方がありがたいのです。よって、再生計画の不履行があっても、それが軽微なもので、かつ、早期に解消するのであれば、債権者もわざわざ取り消しの申立てをすることはないのです。
よって、うっかりして返済が遅れたとしても、すぐさま弁済をして、以後は送れないよう注意しておけば再生計画が取り消されるおそれは相当低いでしょう。もし、事前に期日での弁済が遅れることが分かっている場合には、事前に債権者(弁済代行をしてもらっている代理人弁護士がいる場合にはその事務所)あてに電話して、遅延することを了解してもらっておきましょう。
・債権者による強制執行
さきほど、再生計画の取り消しは、総債権額の10分の1以上を占める債権者だけしか申し立てることができないと説明しました(総債権額とは再生計画による総支払額からすでに弁済された額を控除した残額のことです)。
それでは、再生計画の不履行があった場合、10分の1に満たない債権額の債権者は何もできないかというと、そうではありません。これらの債権者は、訴訟や支払督促の申立てにより判決(債務名義)を取得して、強制執行を行ってくることが予想されます。もし再生計画中に強制執行により給与が差し押さえられた場合、結局、再生計画は実行できなくなる可能性が高いので、再生計画の取り消しの場合とほぼ変わりはありません。よって、せっかく弁護士費用を払って個人再生手続きをしたことが無駄にならないよう、再生計画は確実に実行するよう努力していきましょう。
再生計画の履行が困難になったらどうするのか
もし再生計画実行中に、次のような理由により再生計画の履行が困難となった場合には、特別の手を打つ必要があるので注意しましょう。
勤務先の倒産やリストラによる失職
傷病による休職や失職
回復見込みのない収入や売上の減少
上記のような事情があると、収入そのものが安定して入らなくなるので、再生計画の履行は困難です。そのままだと再生計画が取り消されるのも時間の問題でしょう。
このような場合、以下のような選択肢が考えられます。
①再生計画の変更(弁済期間の延長)
②ハードシップ免責
・再生計画の変更(弁済期間の延長)
民事再生法は、やむを得ない理由で再生計画を遂行することが著しく困難になったときには、再生計画の変更を認めています。具体的には、先ほど挙げた例のように、当初想定していた収入が予想外に落ち込んだよう場合です。
ただし、計画の変更の内容は「弁済期間の延長」のみであり、弁済額の増減は認められていません。また、延長期間も最大2年までという制限があります。
・ハードシップ免責
「再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となった場合、一定の要件を満たしたときは、裁判所は再生債務者の申立てにより、免責の決定(ハードシップ免責)をすることができます。
本来、再生計画を遂行しなかった場合、再生計画は取り消されるので、復活した残債務の免責を得るには、別途、破産手続きによらなければなりません。
しかし、債務者が誠実に再生計画を遂行していたのに、自己に起因しない事情から再生計画の遂行が困難になった場合にまで、原則通りの扱いをして、すべて破産者とするのは酷であるともいえます。
そこで、次のような厳格な要件の下で、特にハードシップ免責という制度を設けたわけです。
(ハードシップ免責が認められる要件)
①再生債務者に起因しない事情によって再生計画の遂行が極めて困難になった場合であること
②再生計画の変更をすることが極めて困難であること
③再生計画で認可決定された再生債権について3/4(75%)以上の弁済が終了していること
④ハードシップ免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものではないこと
上記④の要件は少し分かりにくいのですが、要は、「清算価値保障の原則」を守りなさいという意味です。具体的に言うと、破産と同様に免責を与えるのであれば、せめて、破産手続きを選択していたら債権者に配当されていたと考えられる額までは弁済が終えていることが必要ですよ、という条件です。この条件をクリアしているのなら、債権者は破産手続きをした場合と比べて不利益にはならないからです。
このようにハードシップ免責は、自己破産と同様に借金の免責を認めるという意味で「最後の切札」ともいうべき制度です。しかし、以下の点には注意を要します。
・自己破産よりも厳しい条件が求められること
・住宅ローン特別条項を利用している場合、ハードシップ免責を適用するとこの特別条項は解除となるので、住宅は手放さなければならないこと
まとめ
個人再生をした後、決められた期日に弁済できなかった場合には、まずは債権者に連絡して事情を話し、以後、そのようなことが起こらないように自己管理を徹底しましょう。
他方、予期せぬ事情で再生計画の履行が難しくなった場合には、再生計画案の延長やハードシップ免責の利用を検討する必要があるので、まずは弁護士に相談しましょう。
これらの手続きは複雑であるため、自分だけで行うには限界があるからです。